更新日:2017年08月25日
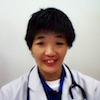
低体温症とは
人間の体温は通常35-37℃程度に調整されており、何らかの原因によってその調整が効かなくなり、深部体温が35℃未満になった状態を低体温症といいます。
*深部体温とは、体の内部の体温で、多くは、直腸で測定し、一般的な体温計を用いて測定する体温とは違います。一般的に平常時の深部体温はワキの下などで測る体温より1度程度高くなります。
たとえば、冬山登山で遭難するなど極端な低温環境に長時間おかれた場合や、中枢神経系に作用する薬を大量に服用していて生理的な体温調整機能が働かない場合、冬場に何らかの他の原因で動けなくなった高齢者が低体温症になって搬送されるような場合などがあります。
低体温症の分類

低体温症は、軽度低体温・中等度低体温・高度低体温に分類されます。それぞれの体温の範囲は、以下のように定義されています。
- 軽度低体温 :35~32℃
- 中等度低体温:32~28℃
- 高度低体温 :28℃以下
軽度低体温(35~32℃)では、全身の筋肉が震え(シバリング)をおこし、体温を上昇させようとします。
中等度低体温(32~28℃)になると、意識が朦朧としてきたり、体温を上げるための震え(シバリング)を起こすこともできなくなったりしてきます。呼吸や脈がやや遅くなります。
高度低体温(28℃以下)では、筋肉は硬直し、感覚もわからなくなり、昏睡し、呼吸や脈が顕著に遅くなり不整脈も起こりやすくなります。
発生原因による分類
一次性低体温症・二次性低体温症という分類もあります。
一次性低体温症(偶発性低体温症)とは、健康な人が、冬山登山で遭難したり、海難事故にあったり、川やため池へ転落したりした場合など、寒冷環境に置かれた際に起こるものです。
二次性低体温症とは、健康な人なら耐えられる程度の寒冷環境下において、頭蓋内出血などの中枢神経疾患や糖尿病や栄養失調状態、自律神経の乱れや大量の睡眠薬などの薬の服用によって、体温調節機能の働きが低下しているために起こるものです。
低体温症の原因
低体温症の原因として、栄養不足、筋力不足、代謝の低下などによって熱を作りだす力が落ちている場合が考えられます。
特に高齢で筋力の衰えが著しい場合、ダイエットで著しく痩せている女性、代謝に関する疾患(甲状腺疾患など)にかかっている場合などで注意が必要です。
また、糖尿病など神経に異常が及ぶ病気にかかっていて、冷たさの感覚が鈍っているような場合には、自覚できないまま凍傷になることや、低体温症になることもあり得ます。
さらには、パーキンソン病や過度のストレスが原因で自律神経に問題が起こると、体温調節機能が上手く働かなくなったり、血管の拡張収縮のバランスが崩れたりするため、低体温症になる場合があります。
その他、ベンゾジアゼピン系睡眠薬やメラトニン分泌を促す薬物は、深部体温を下げる作用があるため、大量に服用することで、低体温症になる場合があります。
上記のように、体そのものの問題によって低体温症になること以外に、寒冷環境から自分の意思で逃れられない状態に陥る疾患や状態も、低体温症の原因として重要です。
寒冷環境を回避できなくなるような状態
寒冷環境が回避できなくなるような状態としては、下記のような可能性が考えられます。
- アルコール中毒
- 脳血管障害
- 外傷(骨折や頸髄損傷など)
- 低血糖性昏睡
- 薬物中毒
- 低栄養による衰弱
- 認知症
アルコールを多量に摂取している場合、糖尿病でインスリンを使っている場合など、寒冷環境から抜けられなくなるようなリスクの高い方に対しては、常に目が届く状態にし、さらに寒冷環境が発生しないように居住環境を工夫しておくことが大切でしょう。
低体温症の症状

低体温症の症状としては、倦怠感、集中力の低下、寒気、体の震えといった症状から、徐々に意識が混濁し、歩けなくなります。さらに進行すると、錯乱したり、幻覚をみたりするようになり、呼吸数や心拍数も低下し、最終的には昏睡状態に陥ります。
症状が進むと震えもなくなる
特に、体の震え(シバリング)は筋肉を動かして熱を産生しようとする体の防御反応ですが、低体温症が進むとそうした元気も無くなってしまい、震えることすらできなくなります。寒さも感じることができなくなり、意識も混濁しているため、極寒の中で衣服を脱いでしまったりすることもあります。
低体温症が放置されると、凍傷がひどくなり、体の組織が壊死(血流不全によって腐ってしまうこと)してしまいます。また、軽度でも神経が障害されて後遺症としてしびれが残ってしまうこともあります。
低体温症の対処法

体温が低下すると、通常体は防御反応として、自発的に「震え」をおこして、熱を発生させようとします。「震え」自体をおこすエネルギーがない場合は震えが来ないまま体温が低下してしまいます。
低体温症に対する対処としては、次の二点が大切です。
- 現在より体温が下がらないようにすること
- 素早く医療機関に搬送し適切に加温をすること
具体的には、体についた水分や霜・雪などを除去すること、冷気から逃れるようにすることを応急処置として覚えておきましょう。意識がはっきりしているような軽症の場合は、温かい飲み物を摂取することも有用です。(※意識がはっきりしない状況での飲食は、窒息や肺炎のリスクがあるため危険です)
医療機関での治療
医療機関では加温方法として加温ブランケットを使用した体表加温や、40℃程度に温めた点滴を投与することによる体内加温などがあります。
また、温水半身浴が有効な場合もあります。※ただし、低体温症に陥っている方に対して急激な加温を行うと、体の外側の血圧が急に拡張するなどして血圧が下がって危険な場合があります。低体温症の程度に応じて、内部からじっくりと温めることが大切ですので、自己流で温めるのは危険です。
意識障害があり、震えの症状がなくなってきている場合(震えを起こす余力もない場合)は、より症状が重いと認識して対応する必要があります。心拍のモニタリング、積極的な外部加温、内部加温、血液浄化療法などを行います。気道確保を要することもあります。
また、循環動態の破綻が認められる場合は、経皮的対外循環補助装置を要することもあります。
低体温症の人の扱い方に関する注意点
低体温症に陥っている方を見つけた場合には、以下のようなことを念頭においておく必要があります。
愛護的に扱うこと
特に深部体温(直腸温など)が30℃以下になると心臓が刺激に対して敏感に反応しやすく死にいたる不整脈を発生する場合が多くなります。心室細動(心停止の1つ)など死に至る不整脈が起きないように、低体温症の方には愛護的に接するということを覚えておきましょう。
頸髄損傷などの併存疾患の可能性を考える
意識障害を伴う場合や、発生状況が不明確な場合は、外傷が併存している可能性があることを想定しておくことが必要です。特に頚髄損傷を積極的に疑い、固定処置などを考慮すべき場合があります。
屋内発見での高齢者低体温症は、併存する救急疾患の可能性を想定する必要があります。適切な加温方法をとるとともに、低体温に至った基礎疾患を早期に検索する必要があります。
安易に死亡していると判断しないこと
偶発性低体温症は生体反応が乏しいため、体温が回復する前に凍死として誤って処置される危険性があります。病院搬送後に適切な処置を行うことで回復する症例も多いので、治療前に安易に死亡していると判断しないようにしましょう。
体温を正確に測定すること
一般に使用されている体温計は、体温が34℃以下の場合は測定できません。そのため、市販の体温計を使用している場合は低体温症を軽く評価してしまう可能性があることを知っておきましょう。
低体温症の予防

低体温症に陥らないために注意すべきことは、しっかりと食事をとり、日頃から運動をして筋力をつけておくことが第一です。
また、保温に努め、寒冷環境に長時間身を置かないようにすること。特に会話に困難が生じた場合は危険ですので、登山中等であれば即座に避難しましょう。
日常生活において特に注意すべきは、飲酒です。アルコールには血管拡張作用があり、体の熱が奪われやすい上、酩酊状態に陥っていると、体が冷えてきていることに気づかず、低体温症になる危険性があります。
また、睡眠薬を常用している人が多量に飲酒すると、薬が効きすぎて昏睡状態に陥ってしまうことがあるため、一緒に飲むことは控えましょう。
なお、喫煙習慣は動脈硬化を進め低体温症に陥った際に危険度が増えるだけでなく、ニコチン自体が血管を収縮させますので凍傷など合併症を増やすことにつながります。低体温症を予防するのであれば禁煙することも大切です。
まとめ
低体温症が発生するのは、冷温環境から逃れられない環境下にあることに加えて、震えによって熱産生を起こすためのエネルギーが枯渇していたり、厳しい気候などによって脱水に陥っていたりすることなどによります。
状況によっては、発症から早ければ2時間程度でも命を落としてしまうことがあるため、重症度を的確に正しく評価し、適切な医療機関を受診する必要があります。
既往症や社会的環境などにより、もともと低体温症に陥るリスクが高いような人は、あらかじめ低体温症にならないように生活環境を工夫しておくことが大切です。








































